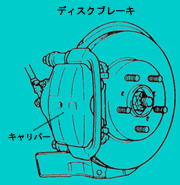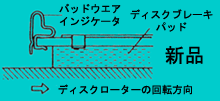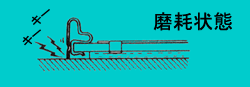パッドは消耗部品として走行距離に応じた点検・整備が不可欠
|
|
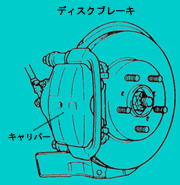
|
ディスクブレーキは車輪と一体で回転するディスクローターを両側からディスク・パッド(摩擦材)ではさみ,その摩擦力で回転を止めて制動します。
ディスクが外気にさらされながら回転しているため放熱性が良く,連続制動・高速走行時に安定した制動力を発揮します。
またペダル踏力に応じて制動するのでドライバーのフィーリングに合った安定した制動力が得られます。
|
|
|
| |
| 劣化のメカニズム |
|
パッドは摩擦材として自らを摩耗させることによって車輪を制動する役割を果たしています。
したがって走行すればするほど摩耗は進みます。
また走行距離が短くても急制動や連続制動,高速走行時の制動などブレーキの使用条件によっても摩耗量は大きく異なります。
また,極めて過酷なブレーキ操作を繰り返すとパッドの表面が焼けて摩擦係数が低下し
“片効き”や“フェード現象”の発生原因となります。
|
|
| メンテナンスを怠ると・・・・ |
|
|
パッドの厚さが規定以下の状態で使用し続けると,急速に摩耗が進行してパッドと接着している金具で直接ディスクをはさむため,制動力の低下を招き大変危険な状態となります。
またディスクを損傷させることにもなり,多額のメンテナンス費用が必要となります。
最近流行の安売り車検等では、この重要な部分の点検整備をしっかりしてもらえず、受験後のトラブルが最も多い原因になる箇所です。
トラブルれば金銭的にも余分な出費がかかりますが、最悪のケースではブレーキが効かず、大きな事故に巻き込まれる危険性もあります。
|
|
| 日常のメンテナンス情報 |
|
現在はほとんどのクルマが摩耗警報装置としてウエア・インジケータ、または警報ランプを装着しています。
これにより使用限界に近づくと,インジケータがディスク・プレートと接触し警告音を発生するか警報ランプが点灯して交換時期を知らせます。
警報ランプタイプは走行前に計器盤をチェックすることが必要です。
なお,こうした警報があった場合,速やかに整備工場等に入庫して点検・整備をすることが必要です。
片効きや引きずりなどの不具合が発生した場合も同様。
いずれにしても安全面、金銭面を考えれば、使用状況に応じた定期的な点検を行い、状況により早めの整備が必要不可欠となります。
|
|
|
| |
| 点検と交換 |
|
〈定期点検基準〉
◆1年点検(自家用乗用車)
※ディスクとパッドとのすき間,※パッドの摩耗
◆2年点検(自家用乗用車)
※ディスクとパッドとのすき間,※パッドの摩耗
※は走行距離項目/検査日または前回点検から走行距離が5000km以下の場合1回に限り省略可。
〈交換の目安〉
一般にパッドの寿命は3〜4万kmといわれるが,ブレーキを踏む回数やドライバーの運転のクセによっても摩耗のスピードは異なる。本来はユーザー自身が走行距離を管理し必要に応じて交換することが望ましいが,自信がない場合は整備工場等で定期的に摩耗状態を点検チェックし交換する。
|
|