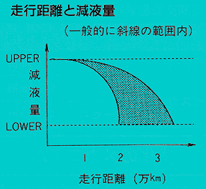|
||||
| 劣化のメカニズム | ||||
|
電解液の減少現象は,充電中の化学反応により起こります。 バッテリーは,充放電の繰り返しにより,極板の劣化(化学反応を起こさない物質への変化)が進むため,十分に充電を行なっても初期の容量には戻りません。 電解液の濃度(比重1.26)や起電力が基準値内にあっても,極板があとどの程度の期間,使用に耐えられるかを判定することは難しい。 ターミナル部の締め付けが,使用期間とともに緩んでいくことはありません。 |
||||
|
|
||||
| メンテナンスを怠ると・・・・ | ||||
|
バッテリー液が不足し(LOWERレベル以下),極板が電解液より露出した状態で使用を続けると,液に浸っていない極板は化学反応しないため著電能力が低下(バッテリー容量低下)し,始動不能などバッテリー上がりの状態に陥ります。 逆に,バッテリー液の入れ過ぎによる液量過多(upperレベル以上)は,旋回時や制動時,または発進時などの車の揺れにより,電解液(希硫酸)が液口栓からこぼれ,付着部分の車体を腐食(溶解)させてしまいます。 ターミナル部の緩みや腐食は,接触不良(接触抵抗増)につながり,各電気系統への供給が断たれ灯火点灯・始動不良などが起こります。
|
||||
| 日常のメンテナンス情報 | ||||
|
バッテリー自体に寿命がくると,充電してもバッテリー液の比重が上がらない,各セル間の比重・量の差が大きい,蒸発が激しい,始動時の電圧低下がひどい(10V以下)などの症状が現れます。 とくに,寿命が近づくと蒸留水を補給してもすぐ減ってしまうため,日頃から液量を確認しておくことが寿命判定の際,重要となります。
|
||||
| 点検と交換 | ||||
|
定期点検基準〉 ◆日常点検(自家用乗用車) 液量が適当であること ◆1年点検(自家用乗用車) ターミナル部の接続状態 ◆2年点検(自家用乗用車) ターミナル部の接続状態
|
||||